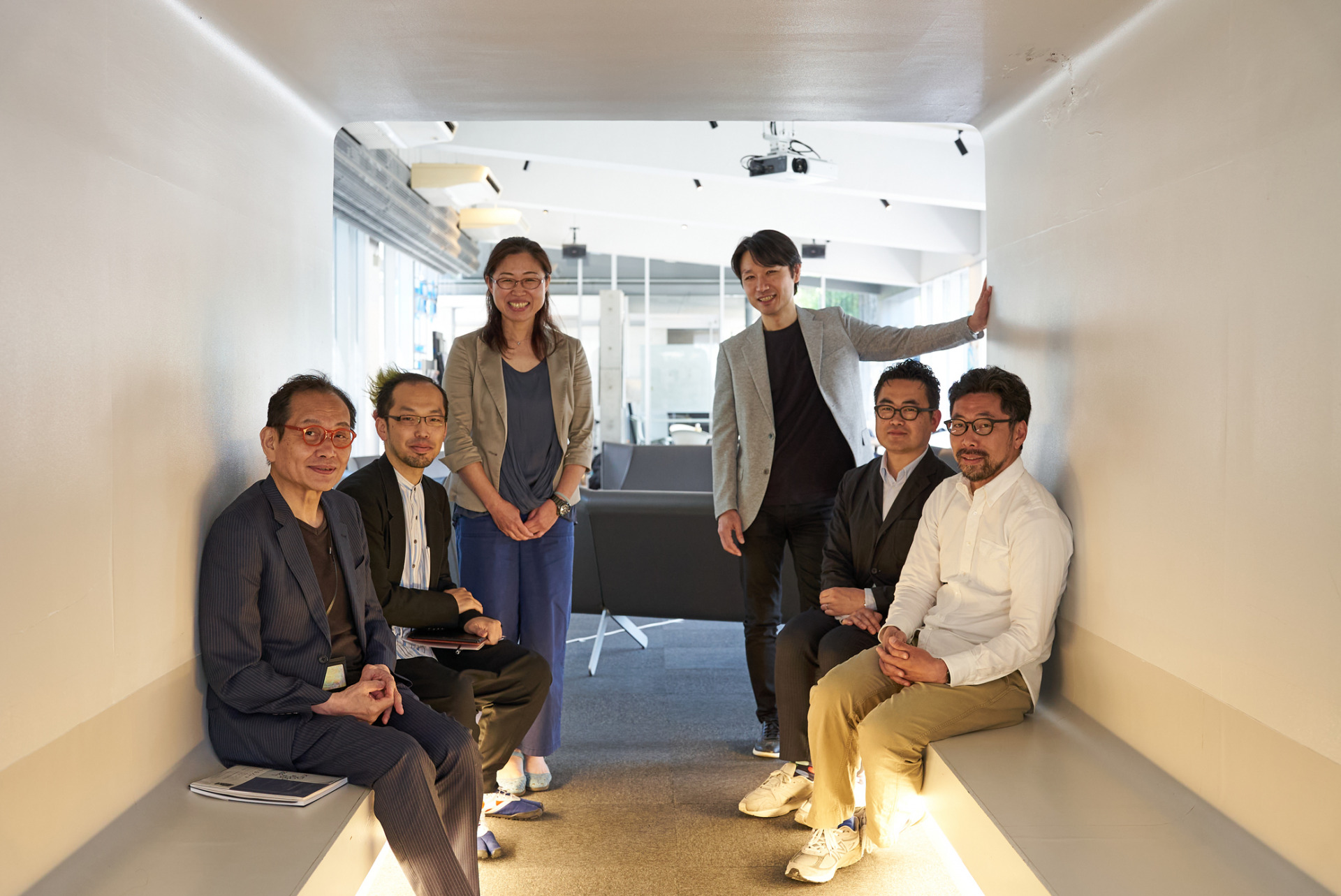
Interview
なぜ未来を考えるのか。深刻化する問題から未来を透視する。
いま、未来を語るために、何を問う必要があるのだろうかーー。
その糸口を探るため、「未来デザイン・工学機構」の設立に深く関わった小野芳朗、水野大二郎にインタビューを行ってきた。語られたのは、今から50年以上前、日本が現在の地球環境問題、人口、観光、都市問題など深刻になり始めていたころに、新京都学派と後に名づけられた梅棹忠夫や小松左京らが構想した“過去の未来”を資産として引き継ぐことと、そして今、この時代に予測不能な社会に対峙するための「6つのCaveats(注意書き)」。
これらの問いかけをどのように実践することができるのか。今回、工学、建築学、言語学、デザイン学など本学所属の4人の研究者が会し、CPFが設立趣旨文として掲げた6つの注意事項をもとに、それぞれの専門領域にある課題と、その解決に向けてどのようなアクションが描けるのかをセッションした。
座談会参加者(五十音順、敬称略):
小野芳朗(本学 名誉教授)
木内俊克(本学 未来デザイン・工学機構 特任准教授)
深田 智(本学 基盤科学系 教授)
水野大二郎(本学 未来デザイン・工学機構 教授)
山川勝史(本学 機械工学系 教授)
山崎泰寛(本学 未来デザイン・工学機構 教授)
Round 04 山崎泰寛「いまの私たちに“見えていないもの”は何か」
「未来は(まだ)説明できない」
山崎泰寛
事前に送られてきた今回の企画書を見たとき、私が座談会の最後の4人目だということがわかっていました。あえて少し挑戦的な言い方になりますが、「未来は(まだ)説明できない」と題してお話ししようと思います。
また、ちょうど先週、先ほど木内さんもお話しされていたヴェネチア・ビエンナーレという非常に大きな建築展が開かれていました。オープニングに同席する機会を得たので、その時の話が、今日みなさんと論じるに値するだろうと。

山崎
展覧会に関わる概念のひとつに「コンタクトゾーン」という考え方があります。これは元々植民地研究のなかで生まれた言葉で、非対称な関係の文化同士が衝突する社会的空間を論じるための考え方です。たとえば、それまで未開の地だといわれていた場所を「辺境」というと、「中心」に対しての「辺境」という関係になる。こうした対照的な関係ではなく、もう少しニュートラルに扱うための言葉として用意されているものです。
これを建築領域に応用して理解するならば、異質な建築文化が出合う場として国際的な展覧会や学術的な学会という場所が考えられます。異なる国同士あるいは民族同士の建築文化が出合う場所を想定して、そのなかでカルチャーのぶつかり合いや相互干渉する文化の移動のあり様を考えていくという視点で建築展を捉えたいなと。
山崎
建築の展覧会は実物を展示できないという大きな条件があるのですが、その方向性は概ね2種類に大別できます。ひとつは著名な建築家の作品を紹介するプレゼンテーション型展覧会。もうひとつは、特定のテーマに対して複数の建築家が参加する特集型展覧会です。日本では、一般的に本が読まれなくなったといわれる2000年代以降に、後者のタイプが増加していきます。
山崎
今日お話ししたいヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展は後者のスタイルで、2年に一度の国際的な展覧会です。今年は「The Laboratory the Future」というテーマを掲げていました。その名の通り未来の実験場として展覧会を定義するもので、右肩上がりの成長モデルを描いてきた先進国の姿勢に批判を向け、経済的には脱炭素化、民族的には脱植民地化を謳う社会派の展覧会です。アフリカの、またはアフリカ系の移民が世界で実践する建築活動や、環境活動など、それまで華々しく建築をプレゼンテーションしてきたビエンナーレが「見落としてきたもの」を問い、多元的な文化のなかで、持続可能な未来をどう思考するのかを議論する場になっていました。
たとえば昨年の美術ビエンナーレで発生した展示用の廃材を集約し、そのリサイクル方法を提案したドイツ館や、菌糸体を用いた建材を開発し、その性能を検証したベルギー館など面白い提案がたくさんありました。
山崎
ただ、ここで私が言いたいのは、ビエンナーレの個々の提案がすばらしいとか参考になるということではありません。そうではなく、ビエンナーレそのものが未来志向の体制であり、継続的に未来を考えていく場を構築することこそをテーマに掲げていたという事実です。それは私には、未来デザイン・工学機構の目指す方向性にとって、ひとつの鏡になるように思えました。
翻って梅棹のテキストや座談会に触れてみると、いくつかの気づきがありました。まず、梅棹が未来に言及するときに、「2050年には」など、年限を区切って話していないということです。環境問題でも少子化問題でも、他国との関係でも、誰と何を話してもただひたすら未来とのみ言う。そこでは例えば22世紀だとか、80年後だとかいう時期を想定させる言い方をしていないんですね。
これは梅棹自身が結局『人類の未来』を書かなかったことと深く関係しているように思います。多くの論者は、梅棹が高すぎる先見性ゆえに未来に悲観的な見通しをもったからだと述べています。これは本当だろうか? 私は違うと思います。
梅棹は出版にあたって執筆メモ(こざね)を大量に残していますが、これを次々と書き足し、入れ替え続けています。
先程お話した建築展も、梅棹が取り組んだ書籍の出版も、知的運動をある段階で一旦区切って形にする側面があります。建築家の磯崎新はそれを「切断」と呼びましたが、梅棹にとっても、出版はある種の切断だった気がします。これは深田先生の議論にあった「説明」についての感覚に近いと思います。説明は現状を「切断」して言語化するものだから、梅棹はそれを避けたのではないか。こざねの作製や編集は、絶え間ない自問自答のプロセスにほかなりません。梅棹にとって未来との関わりは、この終わりのない議論として認識されていたように思います。
つまり梅棹は未来を「説明」するものだとは考えていなかったのではないか。現状で予測できる未来を既知として説明するのではなく、たどり着けるかどうかさえわからない言葉を探して、ひたすら語り続けていたように思うんです。私たちの未来もまた、永遠に終わらない説明以前の議論の場にこそあると言えないでしょうか。そんな問題提起をして、お話を終わりたいと思います。

小野
現状に問題が山積みしているなか、それらを解決する方法がなかったとして、未来の側から逆算して解決を試みていた。でも、その未来がいつかなどとは彼らは設定していないし、必要はない。
かつての大阪万博で、さまざまな企業が妄想とともに色んな未来を構想したんですが、50年経ってほぼすべて実現できたということは、可能性の問題だったのでしょう。50年後の技術というように時を設定してきたわけではありません。
水野
未来の話といいつつ、現代の可能性の話をしているっていうことですね。つまり、今もちうる別の選択肢を提案をしている。可能性を示すために、未来っていう言葉を便宜的に使っていると。
未来技術としてほぼ実現されたものは、すなわち可能性が高かった。さらにいえば、“もっともらしさ”が高いから実現されたとも考えることができます。では一方で、深刻化している問題というのは、その可能性から見過ごされていたんでしょうか?
小野
一行政や、ひとつの国の単位だけでは解決できない問題が含まれていたと思います。日本国内で解決できる問題は、1970年の「公害国会」で法案化されたのでしょう。その時以降起きたのが、都市計画による都市周縁部の山林、海浜、田園、河川敷の開発で、ほとんど価値のない土地に値段をつけて売買し、道路や鉄道と工場をつくった。田中角栄の『日本列島改造論』(日刊工業新聞社)の発行は1972年です。こうした時期に梅棹は「人類の未来」を議論していた。その時は「未来像」を明るく書けないほど深刻な予測をしていたんだと思います。
梅棹忠夫の残した「こざね」よりキーワード抜粋
- 情報産業論
- 人口爆発
- 単線型 線型設計法はあかん
- 科学の限界(証明力の限界)
- ヒューマニズムに対する疑問(反人間主義)
勉誠出版『梅棹忠夫の「人類の未来」暗黒のかなたの光明』より
小野
そして、その予測は当たり、現実に列島改造という名の“破壊”が全国の田舎を襲っていたとき、1979年の大平正芳内閣で9つの政策研究会が立ち上げられ、梅棹はこの研究グループの議長として「田園都市国家構想」を提言した。それは日本文化の特質を生かした都市と農漁村のネットワーク、人間と自然の調和、人と人のふれあいを企図した「反都市計画」「反列島改造」の提案であったわけです。まさに永劫的な「日本の未来」の理想像が描かれたと思います。(中央公論社「梅棹忠夫著作集第21巻・都市と文化開発」田園都市国家構想より)
しかし、大平首相の急逝でこの構想は棚に上げられ、その後のバブル経済と日本の沈滞を生みました。当時、“ありうる未来”を予測できてはいたと思いますが、都市計画と列島改造の力はそれ以上に強大であり、現在も解決不可能な深刻な問題を残してしまったわけです。
水野
深刻化している問題とは解くのが非常に困難であり、そもそも誰が主体となって解くのかもはっきりしていないので見過ごされてきた、もしくは、認識はしていたが解けないので放置せざるをえなかった。深刻化して、難しくても早くから取り組んでおけばよかったという反省が、今あらわれているとすると滑稽ですね。
こうした問題がビエンナーレのような、世界中の人が注目する大きな展覧会の現場で取り上げられているというのが現状であるということですね。
小野
ビエンナーレのような場で、展示された時点で未来はもう明らかなのかもしれません。展示というのは過去、あるいはもうすでに動き出している現実を映し出しているといえます。梅棹の目次とこざねに込められている未来への暗い予感、そしてその後の大平内閣での「田園都市」の議論をみれば「未来はまだ説明できていない」とは到底いえません。50年前には見えていた暗い未来に蓋をして、そして経済不況にもかかわらず、税金で賄う計画都市と開発は進められ、今日にたどり着いた。我々は何を見据えて未来を担う若手に提示できるか、それが大学の為すべき仕事であると思いませんか。
山崎
そのとおりだと思います。「未来はまだ説明できていない」と言いたいわけではなく、未来を安易な説明によって切断せずに、議論を続けることそのものに可能性を感じています。大学がそのためになすべき仕事はこの社会で際立って重要なはずです。
木内
先ほどの問題が深刻化しているという点について思うところがあります。やはりどんな問題も、規模が大きくなればなるほど関わらなければならない主体が増えていくし、それに対して共同で取り組んでいく仕組みをつくることは難しくなる。
これはすでに色々なレベルで健在化している問題で、少なくとも2021年のビエンナーレの時には国単位で展示するというこの形式自体を問い直す議論があったんです。もはや国単位で情報交換をしている場合ではなく、ビエンナーレを国際的な構想の作業場だと考えるぐらいのスタンスでなければ、このように多くの国が一堂に会する意味がないのではないか。

木内
いかにビエンナーレという場を、国際間で連携しなければできないようなことに取り組むための足がかりとするか。具体的にどう連携するかということを、若い世代で考えていかなければなりません。
ビエンナーレという場所でできたネットワークを以って、どういう別の仕組みを考えればこれまで共創できなかった主体同士がある特定の問題にコミットできるのか。そういうことを考えることが、いま一番重要なトピックになっているんじゃないかと思います。
山崎
今年のビエンナーレで金獅子賞を獲ったのはブラジル館でした。これをどう評価するのかは賛否両論あると思うんですけども、彼らが何をしたかというと、ブラジルでおこわれてきた森林の伐採による環境問題、ブラジリアという都市の乱開発に伴う諸問題、民族に対するひとつの抑圧的な態度みたいなものを、なるべく本人たちなりに隠さないようにして、過去と今がどう共存していくのか。そのようなテーマをもった展示空間が成果とされました。わかりやすく政治的にも評価された、といってもいいかもしれません。

山崎
もはや考えることすら放棄しているような深刻な問題への対処として、これがヒントになるかわかりませんが、昨年、KYOTO Design Labで行われた授業の話を。
世界的に非常に著名な編集者でありデザイナーでもある、パブリッシャーのラース・ミュラーが来日し、学生とともに京都をもう一度見直して再構築するというワークショップをなさいました。
そこで彼が何度も繰り返し伝えていたことが、「人は見たいものしか見ない」ということでした。人は見たいものを見て、見えたものでしか判断しない。本当にいま見てるものが「すべて」なのかと。あまりにもそればっかり仰るので、強く印象に残ったんです。
「未来は(まだ)説明できない」というテーマでお話ししましたが、いまの私たちに見えていないものがあるとすれば、それは何なのか。梅棹さんらが延々と議論を重ねたように、今日のような場から気付くものだと思いました。
本サイトがCookieを利用する目的については、Privacy Policyをご確認ください。
